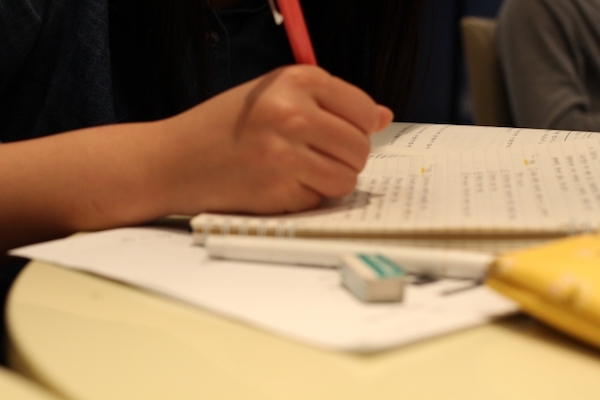
ADHDやLD、アスペルガー症候群など発達障害のお子さんは、数学が苦手なことがあります。数学は普通のお子さんもわからなくなることがよくあり、発達障害・学習障害のお子さんだとなおさら。
ただ、発達障害でも数学を理解することはでき、中には得意な人さえいます。1歩ずつ勉強すれば克服できるので、これから頑張ってみましょう。
ここでは「発達障害の数学勉強法」を解説します。
発達障害の子供には数学が得意な子もいれば、苦手な子もいる。つまり個人差あり
まず、発達障害だからといって、絶対に数学ができないわけではありません。ADHDやLD、アスペルガーのお子さんの中には、数学が理解できる人もいれば、「むしろ得意」という人もいます。
要するに「数学の学力には個人差があり、本人に合わせた勉強をすることで克服できる」ということです。
ではどうすれば数学の学力を伸ばせるのか?ここから解説します。
発達障害で数学が苦手な場合、どうすればできるようになる?5つの方法
発達障害で数学が苦手なお子さんは、下の5つのポイントに気をつけて勉強すると良いです。
【発達障害のお子さんの、数学勉強法】
- 数学の基礎力は「計算」。まずはカンタンな計算の反復練習を繰り返す
- どこから理解できなくなったのか確認して、そこから基礎を勉強し直す
- 数学になると集中できないときは、10分や15分など、短い時間に区切って勉強する
- 公式がどうしても暗記できない場合、「どうやってこの公式が作られるのか」を理解する
- 「発達障害は数学ができない」という思い込みを外す
数学の基礎力は「計算」。まずはカンタンな計算の反復練習を繰り返す
数学は連立方程式や図形、2次関数など、たくさんの分野があります。ただ、数学の基礎力は、「計算」。計算がスムーズにできることで、内容を理解しやすくなります。
計算ができないと新しい内容を学ぶとき、計算で止まってしまいます。本当に理解するべきポイントがあっても計算でつまずくと、学習が思うように進みません。
そのためまずは、計算の練習をしましょう。確認するべきなのは、小学校4〜6年と、中1の前半で出てくる内容です。
【まず押さえておくべき、主な計算】
- 足し算・引き算・かけ算・割り算(小学校)
- 分数の計算(小学校)
- 少数の計算(小学校)
- かけ算・割り算のひっ算(小学校)
- プラスマイナスの足し算・引き算・かけ算・割り算(中1)
- 文字の式(中1)
- 方程式(中1)
- 数字の代入(中1)
ひとことで計算といっても、上のように幅広い内容があります。それぞれをできるようにしておかないと、「この計算、どうだったっけ・・」とつまずいてしまいます。
上の各項目を「ちゃんと計算できるかな」とお子さんに確認してみてください。「プラスマイナスの計算は、たしかにできないかも・・」となっていたら、その分野から計算練習をすると良いです。
本屋に行くと、計算練習ができる問題集が売っています。また、学校のワークで計算のところだけ解き直すのも良いです。無理に難しい計算をせず、数をこなして練習すると速くなるので、ゲームのように反復しましょう。
どこから理解できなくなったのか確認して、そこから基礎を勉強し直す
数学がわからなくなっても、学校の授業は先に進んでしまいます。ほかの生徒さんがいる以上、仕方ないことではあります。
ただ、学校で進めている内容を理解しようとせず、まずは「どこからわからなくなったのか?」を確認しましょう。
数学は階段のように、中1・中2・中3・高1・高2・高3と、少しずつレベルが上がります。もちろん小学生の「算数」からわからなくなっている可能性もあります。
「小学校までは理解できた。でも中学校に入ってからわからなくなった」という場合、中学のどこでつまずいたのか突き止めるのが効果的です。
以前はわからなかった内容でも、振り返ってみると理解できることはよくあります。今はより難しい内容を勉強してはずなので、前の内容はカンタンに感じるためです。
「数学は苦手」というお子さんは、漠然と数学全体を「ムリ」と決めつけていることが多いです。ですがそうではなく、理解できなくなったところからやり直せば、またわかるようになるはず。学校の内容は最低限だけでも押さえて、復習に力を入れましょう。
数学になると集中できないときは、10分や15分など、短い時間に区切って勉強する
ADHDやアスペルガー症候群などのお子さんは、興味がないことに集中できないことがあります。
数学の勉強に集中できない場合、10分や15分など、短めの時間で区切りましょう。10分でもきちんと勉強して理解できれば、「自分でもできた、わかった!」という自信がつきます。これが「もう少しやろうかな」という次につながり、より長時間の勉強ができるようになります。
いきなり「毎日1時間、数学を勉強しよう」と高いハードルを作っても、すぐに諦めてしまいやすいです。タイマーで時間を測ったり「ごはん前の15分で勉強する」のと決めたりして、少しずつ勉強時間を増やしましょう。
公式がどうしても暗記できない場合、「どうやってこの公式が作られるのか」を理解する
発達障害のお子さんは、暗記が苦手なこともよくあります。
数学は論理的に考えることが多い科目ですが、公式は暗記する必要があります。公式がなかなか覚えられない場合、「なぜこの公式が成り立つのか、どうやって作られるのか?」を理解すると良いです。
数学の教科書には、「こういう仕組みで、この公式が出てくる」という説明(証明)が載っています。これを読んで理解すれば、公式が意外と思い出しやすくなります。
ただし公式の証明は、難しいことが多いです。下でも紹介しますが、「スタディサプリ」の動画で学んだり、家庭教師の先生に説明してもらったりするとスムーズです。
「発達障害は数学ができない」という思い込みを外す
上でも触れていますが、発達障害のお子さんは「ADHDだから、数学は頑張ってもムリ!」と決めつけてしまっていることがあります。ですがそうではなく、原因を突き止めて基礎からやり直せば、理解できます。
たとえば「1+1」という計算は、「さすがにできるよ」という人が多いはず。「5✕7」というかけ算でも、ぱっと出てくることは多いでしょう。
つまり、どこかでつまずいたポイントがあるわけで、それまではきちんと理解できていた、ということ。「ここからわからない」という内容をピンポイントで見つけて、復習しましょう。
発達障害の数学学習におすすめの教材・サービス
数学を自分で勉強するのは、なかなか大変なもの。発達障害のお子さんは、なおさらです。
本格的に数学を頑張ろうと思ったら、教材や学習のサービスを利用するのが効果的。下の2つは特におすすめなので、考えてみてほしいと思います。
「スタディサプリ」の動画授業はわかりやすく、繰り返し学べる。しかも月2,178円(税込)とお値打ち

スタディサプリは大手企業のリクルートによるサービス。有名な予備校の先生による動画授業を見て、スマホやタブレットで勉強できます。
スタディサプリは基礎からわかりやすく解説されていて、動画なので途中で止めたり、繰り返し見たりすることができます。動画は1つ10〜15分ほどで集中力が続きやすく、ちょうど良い長さ。自分のペースで授業を受けられるような感覚で、発達障害のお子さんにも使いやすい教材です。
さらにスタディサプリは数学だけでなく英語・国語・理科・社会も中1〜中3、さらに小学生の内容まで全て勉強できて月2,178円(税込)とお値打ち。1年間の一括払いなら10,780円(税込)と、さらにオトクです。
スタディサプリは14日間の無料おためし期間があり、この間に解約すれば料金はかかりません。もちろん続けて使うと良いサービスですが、まずは自分に合っているかやってみるのもおすすめです(※無料期間は申込日が1日目)。
家庭教師は1対1でじっくり教えてもらえる。英語や勉強の仕方まで指導

家庭教師は先生に1対1で教えてもらえるため、効果の高い学習方法。発達障害のお子さんに合わせて教えてもらえて、発達障害向けコースを用意している会社もあります。
また、家庭教師は数学だけでなく英語やほかの教科も教えてもらえて、「こうやって勉強するといいよ」という勉強の仕方まで指導してもらえます。優しい雰囲気の先生や面白い先生など、さまざまなタイプの先生がいるため、希望を出すのも良いです。
家庭教師は大手のトライだと高いですが、最近は良心的な価格の会社も増えています。もちろんスタディサプリは値段が高くなりますが、体験授業を受けて考えてみるのも良いでしょう。
多くの家庭教師センターは無料で体験を受けることができ、お子さんに合わせた学習のカウンセリング・アドバイスも受けられます。別ページでおすすめの会社を紹介しているため、合わせて参考にしてほしいと思います。
(参考)家庭教師は発達障害のお子さんにもおすすめ。料金目安・注意点と評判の良いサービス5社(オンライン含む)
発達障害でも、数学は克服できる!1歩ずつ、じっくり勉強しよう
ADHDやLD、アスペルガー症候群など、発達障害のお子さんでも数学はできるようになります。どこから理解できなくなったかを振り返り、まずは計算の反復練習から始めると良いです。最近はスタディサプリなどの良質な教材もあり、きめ細かく教えてほしいときは家庭教師も考えると良いです。
1歩ずつじっくり進めれば、きっと数学の苦手を克服できるはず。焦らずじっくり頑張ってほしいと思います。